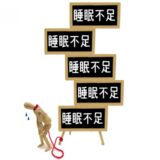日々のお仕事お疲れ様です! ぽり です!
気づけば夕方。「なんでこんなに疲れてるんだっけ?」と考える間もなく明日の準備。
気力も残ってないのに、また電話が鳴る——そんな毎日に、覚えがありませんか?
福祉の仕事って、気づけば“やること”ばかり増えていきませんか?
支援の質を高めたい、利用者に誠実に向き合いたいと思うほど、タスクも会議も書類も増える。
そして、いつの間にか自分のエネルギーが枯渇している——。
そんな毎日に限界を感じ、「“やらないこと”を決める」という視点を取り入れてから、
支援にも働き方にも大きな変化が生まれました。
「やらないこと」を決めたきっかけ
福祉の現場では、「自分がやらなきゃ」という意識が強くなりがちです。
それが職場や利用者のためになることも多い反面、全てを自分で抱え込む働き方は、
いずれ心も体も疲弊させてしまいます。
実際に私は自分でやらなくてはと思い走り続けて限界に達し、
「自分には合っていないのかも。もう仕事をやめてしまいたい。」
と考えたことが多々ありました。
1. 電話対応を“すべて自分でやる”のをやめた
以前は、関係機関や利用者から自分宛てにかかってくる電話にはすべて自分で対応していました。
「名指しされたら自分が出なきゃ」という思い込みがありましたが、
業務がひっ迫したある日、他の職員に一時的にお願いしたところ、
最初は内心ヒヤヒヤしながら他の職員にお願いしましたが、
『誰が対応しても問題なかったですよ』と報告を受け、安心したのを覚えています。
正直、意外と支障なく対応してもらえたことに驚きました。
その後、私宛ての連絡について改めて精査してみたところ、
多くは内容を分類すれば汎用的なもので、個別対応でなくても成立することに気づきました。
実際、自分でなくても済む問い合わせは多く、
「対応可能な範囲を共有すること」さえしておけば、
他の職員でも十分に対応できる内容が大半だったのです。
自分にしかできない内容だけ引き受ける
まずは他の職員に対応して、必要に応じて対応するフローに変更
こうした線引きをすることで、本当に集中すべき支援業務に時間を使えるようになりました。
2. すべての会議に出るのをやめた
「呼ばれたら出るもの」「聞いておいた方がいいかも」と、
すべての会議に出席していた頃は、自分の業務にはあまり関係ない会議で貴重な時間を消費していました。
そこで、
- 事前に議題と内容を確認
- 必要な会議だけ出席
- それ以外は議事録でフォロー
というスタンスに切り替えました。
結果、浮いた時間を資料整理や支援計画の見直しなど、
“中身のある時間”に変えることができたのです。
「任せる」ことは「丸投げ」ではない(注意)
電話対応や会議の出席を減らすには、当然ながらその分のタスクを他の誰かにお願いする場面も出てきます。
そのため、「やらないこと」を決めるときに大切なのは、周囲との信頼関係やバランス感覚です。
私自身、ただ自分の負担を減らすだけではなく、逆に他の職員が困っているときにはこちらから手を差し伸べるように意識してきました。
そうした“持ちつ持たれつ”の関係があるからこそ、業務をスムーズに回すことができます。
「これは自分でなくても大丈夫」と判断できるタスクを手放す一方で、
「これは自分が得意だから引き受けたい」「時間がある今こそサポートに回ろう」
そんな姿勢を持つことで、お互いにとって無理のない働き方の形が見えてくるのだと思います。
支援の現場はチームで動く仕事。
「減らす」ことは個人のためだけでなく、チーム全体のエネルギー配分を最適化することにもつながります。
減らすことで、支援の質が上がる
「やらないこと=無責任」ではありません。
むしろ、大事なことに集中するために、あえて他を減らす。
これが、私の働き方の基準になっています。
・支援の記録にじっくり時間をかけられる
・他の職員に手を差し伸べる余裕が生まれる
・利用者との関係性が丁寧に築ける
まとめ|明日の「やらないこと」を、ひとつ決めてみませんか?
「やらないことを決める」のは、支援の手を抜くことではなく、
“本当に必要なことに集中する”選択です。
まずは明日の朝、「やらないことリスト」をひとつだけ決めてみてください。
きっとあなたの働き方に、少しの余白が生まれるはずです。
本ブログでは福祉職で働く私が実践してきたシンプルに暮らすための情報を発信しています。
これらを読んで実践していただくと気持ちが楽になり、もっと自由に楽しく暮らせるようになります。
ぜひ他の記事もご覧ください。
それでは良い一日を。
 ぽりの提案ブログ〜シンプルな働き方のススメ〜
ぽりの提案ブログ〜シンプルな働き方のススメ〜